黒森山浄仙寺登り口の付近で、中野川から取水した堰(せき)が、山形地域の山腹や山麓を蛇行して長坂集落の分水口にさしかかると、その脇に古い石碑が建っている。今から約160年前の1827(文政10)年に建てられた碑で、刻まれた字は風雨にさらされてかなり読みにくくなっている。
碑の正面には大きな字で「田山堰神祠(たやまぜきしんし)」と刻んであって、その左右には小さい字で、田山藤左衛門が万治年間(1658~60)に弘前藩の命を受けてこの堰を完成させたので、この堰のことを田山堰と名づけたという由来が刻まれている。

碑の裏には、この堰の恩恵を受けてきた弘前藩領浪岡組の六郷の村々(上十川・赤坂・三島・高館)の庄屋の名と5人組の百姓の名が何人か刻まれている。この石碑は、六郷の村人たちが、堰の開削者田山藤左衛門への感謝の気持ちをこめて建てた石碑である。
さらに、この碑の脇には、山形の村々の分水取入口の寸法も刻まれている。このことから、田山堰の恩恵を受けたのは、六郷の村々だけではなく、黒石領の山形地域の村々も、この堰から分水して水田耕作を営んできたことがわかる。黒石領の山形の村人は、どういうわけか、田山堰のことを小川堰と呼んでいた。
さて、田山堰開削の工事はいつ始まっていつ終ったのだろうか。長坂の石碑には、万治年間に田山藤左衛門が開通させたとあるので、水路の幹線が完成したのは1660(万治3)年と見てよい。
工事の始まりについては、石碑は語っていないので、古い記録から推測するしかない。田山堰土地改良区で発行した『田山堰沿革史』という本に古い記録が紹介されている。その中の水争いの時の農民たちの「口書(くちがき)」(江戸時代の訴訟関係の文書の名)が参考になる。
1688(貞享(じょうきょう)5年の「口書」を読んでみると、1656(明暦2)年、津軽信英(のぶふさ)が5000石を与えられ、黒石に分家した後に、本家の弘前藩と分家の黒石陣屋が人夫を出し合って、共同で工事を進めたとある。このことから、工事の開始は1656~57(明暦2~3)年だということがわかる。こうしてみると、工事は3~4年かかったわけである。
それでは、田山藤左衛門という弘前藩士は、この時期に六郷の村々とどういうかかわりがあったのだろうか。

1650年代の明暦年間、津軽平野の開発は急ピッチで進められていた。現在、青森県の穀倉地帯といわれる西津軽郡・北津軽郡の岩木川下流地帯は、この頃開発された。六郷に派立・派立子という通称の地名があるが、それは、この頃の開田事業の名残りである。六郷の藩営による開田を指導するために、弘前藩から派遣されたのが田山藤左衛門である。藤左衛門の妻は、三代藩主信義の二女であったところからして、普請(ふしん)奉行とかの責任ある役職に任ぜられたのではないだろうか。
六郷地帯は、それまで長谷沢(ながやさわ)の沢水を集めたり、十川(とがわ)の自然流水を使用したりして、いくばくかの水田を営んでいたが、開田のためには新たな水源を見つけ、水利の便をはかる必要があった。新たな水源として、田山藤左衛門たちが目をつけたのは、年中水量の豊かな中野川であった。よく考えてみれば、これは先見の明がある素晴らしい計画であった。
中野川から六郷までは13キロ(約3里)もあり、開削工事は大変苦労するわけだが、そこを流れてくる水は、日にあたって適度に温められ、作物の成育に大変良い結果をもたらすことを、藤左衛門はよく知っていた。
「工事はつらいが獲物は大きいのだ。」といつも自分に言い聞かせながら、藤左衛門は計画を具体的なものにしていった。
まず、この計画では、黒石領内に取水口を求めることになるので、初代の黒石領主津軽信英の承諾を得る必要があった。幸い、津軽信英は弘前四代藩主津軽信政の叔父にあたり、信政の後見人でもあったので、何ら問題なく認可された。信英にしてみれば、この堰の途中から分水すれば、山形の村々の開田も可能になるのだから、むしろ、藤左衛門を励まし、協力すべきだと考えたかもしれない。
工事を開始するまでの藤左衛門の調査活動や計画書づくりの苦労話は、何も伝わっていないので、想像してみるしかない。堰の取水口を井戸沢の所に定めるまでには、何回も何回も慎重に調査を重ねたことであろう。自然流水で六郷まで、できるだけゆるい勾配で水を運ぶにはどうしたらよいのか、また放水路をどこにするかが検討され、さらに地質の調査もなされたはずである。工事を始める前の設計が、工事の成功・失敗を決めることになるので、藤左衛門以下の担当者たちは、精力的に山野を調査し、図面をつくっては検討を重ねたにちがいない。

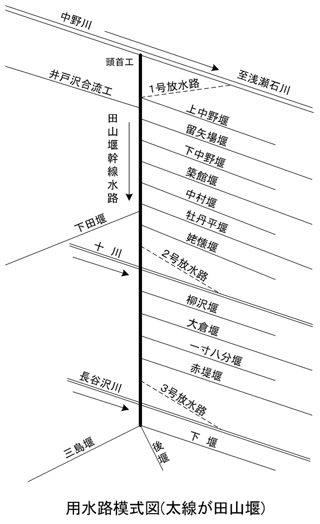
その他に、工事人夫の動員計画や費用の見積りの仕事があるが、田山藤左衛門という人は、1660年代(寛文年間)に、勘定奉行(かんじょうぶぎょう)配下で御金奉行(ごきんぶぎょう)をつとめている人なので、見積りは得意な仕事であったようだし、動員の方は黒石領主の協力が約束されたので、心配はなかったと思われる。
かくして、1656~57(明暦2~3)年頃に開削工事が始まるわけだが、弘前藩の藤左衛門たちが動員した人夫は延べ5000人、黒石陣屋で動員した人夫は延べ3000人であった。
人夫といっても、ほとんどは農民であった。田山堰を歩いてみればわかるのだが、流れをゆるやかにするために、所々に段差を設けて小さな滝のようにしてある。藤左衛門たちがいかに頭を使ったかがわかる。
難工事は何といっても、山形の高清水山の山腹開削の工事で、岩石の多い石山の開削をのみやつるはしだけで掘ることは、想像以上の苦しみであった。1981(昭和56)年に、東英中学校演劇部で発表した「田山堰物語」の舞台でも、この高清水の難工事の場面が中心になっている。
この物語は、元中郷中学校教諭鎌田與一郎氏の原作によるものであり、すべてが史実にもとづいて作られたものではないが、田山堰の開削工事の状況やそれにたずさわった人々の苦難の様子がよくうかがわれる。次にその一部を紹介する。
「田山堰物語」 第二幕より
・1657(明暦3)年の夏
・堰の工事現場
・工事人夫
飛内村の孫六
目内沢村の与作
花巻村の千吉
馬場尻村の半蔵
出石田村の多助
野添村の弥七
福民村の甚八
・彦兵衛(花巻村の庄屋)
・良庵(田代山の僧)
良庵は田代山に一人で住んでいるが、向い側の黒森山を眺めて常々考えていたことがある。
「このままでは日照りに泣く村々は決して救われることはない。何とか救う方法はないものか。」
「ところであの高い黒森山は、あの山腹に十分な水を貯えている。そして絶えず水を吐き出している。」
「沢に集まった水は急流となって流れ、中野川に注ぐ。中野川は浅瀬石川にのみ込まれる。しかし、中野川も浅瀬石川も村よりははるかに水位が低い。村人達は、せっかくの水もくみあげることができない。浅瀬石川の水は、あざけり笑うかのごとく流れ去っていく。」
「日照りに泣く村人達を救う方法は……。そうだ。黒森山の水を中野川に流さないことだ。黒森山の水をそっくり利用する堰を作ることだ。」
「まずトサバ尻の上に水を集める。それから高清 水の山の中腹に堰を通して運ぶ。*(がむし)の峠の向い側だ。野添、目内沢から飛内、馬場尻方面の田んぼは、一面豊かな水量でうるおされる。」
*→上が我、下が虫
「さらにいいことがまだある。高清水の中腹を通る堰は南向きだ。流れる水はお天とう様に温められる。温められた水は稲を豊かにみのらせる。山から直接引く冷たい沢水よりも、何倍も収穫の量を増やす。花巻の村もうんと助かるはずだ。」
「掘る堰の長さは、距離にしておよそ3里(1里は約 4キロメートル)に及ぶだろう。完成までの期間は年月にしておよそ7、8年、いや10年は要するかも知れぬ。」
工事にあたっている人夫達は、仕事が大変きついので、ひと休みする度に「あすからやめたい。」、「こんな仕事はまっぴらだ。」、「もうへとへとだ。」と苦情を言い合った。
孫六「なあ、みんな聞けよ。おれ達はだまされているのだ。そうだろう。毎日毎日こんなに苦しんでいるのによ。仕事はちっともはかどらねえ。どだい無理なんだこの工事は。初めから無理だってことがわかっているのに、おれ達は無駄働きさせられていたんだ。その証拠には、賢いやつらはさっさとやめていったじゃないか。」
一同「そうだそうだ。だまされていたのだ。おれ達はだまされていたのだ。」
孫六「花巻の庄屋め、いい理屈こきやがって。水は分けてやろう。その代り新しい堰を作ろう。この堰ができたら、おめえ達の村も水不足で苦しむことがなくなる。」
半蔵「それどころか、その水で新しい田もどんどん作れる。」
弥七「5つも6つもの村の衆が、みんなの力を合わせりゃわけはねえっておだてやがった。」
与作「おれ達は牛や馬のように、いっしょうけんめい働いた。」 多助「だけど、高清水の石山がこんなにも固い岩盤だとは思わなかった。工事は予定の半分の半分も進まねえ。」
甚八「それだけじゃねえ。石がくずれ落ちてきて、これまでに何人も人が死んだ。犠牲の人柱まで出ているのだ。」
この石山工事のつらさは、藤左衛門たちが調査した段階で予想されていたことではあったので、彼は心を鬼にして人夫達を叱咤激励(しったげきれい)したに違いない。
「今つらくても豊かな稔りが待っているのだ!子孫のためにも耐えてくれ!」
伝承では使役が苛酷で、かくれた犠牲者もあったという。犠牲を無駄にしないためにも、藤左衛門は一層気をひきしめて石山に挑んだ。そして、信念は岩をも貫いたのである。13キロメートルの水路工事を、3~4年で完成できたのは、設計が正しかったことと掘り抜くという不動の信念、そして農民たちが苦しみに耐えて休まないで掘り続けたその根気によるものであった。苦労が大きかっただけに、田山堰の恵みは時代が進むにつれてますます大きくなっていく。
浪岡組六郷地域の開田は、1684~87年の貞享年間に113町歩であったが、1801~3年の享和(きょうわ)年間には142町歩(1町歩は約1ヘクタール)に増えている。
一方、黒石領の山形地域の村々は、1660(万治3)年に完成した田山堰(黒石領では小川堰と言った)の幹線水路から次々に分水し、山麓部の開田を進めた。1678(延宝6)年頃には、惣兵衛堰(そうべえぜき)・田ノ沢口(いずれも中野)、惣一郎堰・覚左衛門堰(いずれも花巻)、堤沢口(つつみざわせぎ)(温湯)、境沢口(下山形)、惣十郎堰(石名坂)などの分水堰ができており、1683~87(天和3~貞享4)年の間に、下田堰・牡丹平堰・姥懐堰(うばふところぜき)(いずれも牡丹平)の3筋の新しい分水堰が完成した。 田山堰からの分水によって、山形地域の開田面積は、1850(嘉永3)年までに81町歩に及んだ。
山形地域の村々が田山堰に分水口をつくって取水するようになると、当然起きてくるのが下流の六郷地域の村々との水利をめぐる争議(水論)である。『田山堰沿革史』には、1687~88(貞享4~5)年頃の水論の時の農民たちの口書が紹介されているが、争点になっているのは、分水口の寸法の問題であった。
この水論は、明治になっても続く。最初に紹介した長坂の石碑の脇に刻んである各取入口の寸法は、水論の時の判断の基準ともなったわけである。
さて、田山堰の工事を終えた後の藤左衛門はどうなったのだろうか。藤左衛門に関する数少ない断片的な記録から推測してみることにしよう。
「津軽家御定書」という史料によれば、1668(寛文8)年当時、田山藤左衛門は弘前藩の御金奉行をつとめていた。御金奉行というのは、勘定奉行の支配下にあって、金銭の出納事務にあたる役職である。田山堰開削の功績によるものであろう。御金奉行をいつからいつまで勤めたかは不明であるが、堰の工事が終ってからだから、早くても1661(寛文元)年からであろう。終りの方は、長く勤めたとしても、1680(延宝8)年までである。
御金奉行を退任した後、藤左衛門は郡奉行(こおりぶぎょう)を勤めている。「永禄日記」という文献によれば、1682(天和2)年に郡奉行を退任している。郡奉行は定員3人で150石の禄高(ろくだか)である。生産の増大をはかり、年貢米を徴収する役目である。その下に代官がいた。
こうしてみると、田山藤左衛門という人は、土木→会計→農政という内容の違うさまざまな仕事を次々と成し遂げてきた器用で勤勉な仕事人という感じがする。何をやらせてもきちんとやり遂げるものだから、仕事が切れることはなかった。
藤左衛門の最後の仕事は、六郷に近い所にある北黒石4ヵ村(飛内・小屋敷・馬場尻・下目内沢)に関する仕事であった。
1689(元禄2)年、黒石津軽家の分家に後継ぎがなく御家は断絶し、分家の知行地1000石は幕府領(天領)となった。1000石の内訳は、北黒石の4ヵ村500石と上州(群馬県)の飛び領500石である。飛内・小屋敷・馬場尻・下目内沢は1689(元禄2)年から1698(元禄11)年までの9年間天領であったわけだが、その間の年貢徴収の事務は、本家の黒石陣屋ではなく、宗家(大本家)の弘前藩に委託された。
そこで登場してくるのが田山藤左衛門である。藤左衛門は六郷に縁のある人だから、六郷に隣接している北黒石4ヵ村の内情にも通じていて適任と見られた。
飛内の高木家に残っている元禄時代の年貢関係の文書には、たいてい田山藤左衛門の署名と印がある。しかし、彼の署名が見られるのは1695(元禄8)年までで、翌年以後の文書には、もう彼の名は見られない。仕事人藤左衛門も、寄る年波には勝てなくなったようである。藤左衛門がいつ生れていつ亡くなったのかは明らかでないが、1695年の時点では、もう65歳も過ぎていただろう。さまざまな仕事を確実にこなしてきた40数年間の多忙の日々を、静かに回想する晩年であった。
さまざまな思い出の中で、藤左衛門の脳裏を片時も離れなかったのは、あの壮年の日に、寝食を忘れて取り組んだ堰の工事のことだったに違いない。
「あの頃は俺も若かったし、百姓衆もよくやってくれた。死んだ人も山形や六郷の田んぼを見れば成仏してくれるだろう。」
藤左衛門が田山堰から眼下の水田を眺める時、彼は亡き人々と一緒に眺めていたのである。
(執筆者 七尾美彦)

(田山堰の流れ)