
声の大きい男
うだるような暑さの夏の昼さがり、死んだような静けさの山道を登って来て、ふと立ち止った。音がするのである。たえまなく続いているので気がつかなかったが、じゃわじゃわ、じゃわじゃわ、異様な音がする。さて、これはなんの音だ?登って来た人はあたりを見まわした。そして髪が逆立ったかと思うほどびっくりした。毛虫なのだ。毛虫がりんごの木に群がって葉を食っているのだ。広いりんご園の木全部が無数の毛虫の食害にあっていたのだ。
あまりのひどさに、その人は逃げるようにそこを去ったが、もし彼が呆然と見続けていたら、もっと恐ろしい光景を目にしたに違いない。葉を食いつくした毛虫の大群が、道を隔てた隣のりんご園に移動するのである。黒い大きいじゅうたんがもくもく動いていくような異様な光景に恐怖の声をあげたであろう。
1945(昭和20)年敗戦で降伏した年の、手がまわらないで放棄されたりんご園の姿はこのようなありさまであった。戦争に男手をとられ、農薬や肥料の配給は全くなく、荒れるがままにするほかなかったのである。この年の青森県の生産量はわずかに3万6千トン。平和な時代の平年作の10分の1でしかなかった。
りんごは津軽の山村の農民生活を一変させた金(かね)のなる木であった。昔の山の民の生活というものは、北も南もない、一様に貧しいものだった。
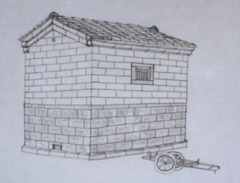
それが津軽の山村だけは、あれよあれよという間に、よい家が建ち土蔵が建ち、石倉まで建つようになった。それはりんごのおかげである。もう一度その生活を取り戻さねばならぬ。人々はいっせいにりんごの復興を願った。さてどうすればいいのか。戦争は終わっても物資の欠乏はむしろひどくなるばかりだ。
この時、彗星のように一人の男が現れた。「害虫や病気で弱った木は切って焼いてしまえ。」
「残った木を大事に育てよ。」
「守る姿勢だけではだめだ。新たに畑を開いてどんどんりんごを植えろ。」
その男は、自信に満ちた態度で、わかりやすい言葉で、大きい声で、人々を励ました。実際その声は千人の大衆にマイクなしで話しても、隅々までよく通るほどの大声であった。
もともと、彼は県農業会の優秀な職員として、関係者の間では注目されていた。そして今、りんごの荒廃から立ち上がり、再びりんご王国青森を築こうという機運の中でリーダーに押しあげられて、その豊かな経験と秀れた素質が一気に開花したのであった。そして、りんご120年の歴史に、昭和戦後りんご復興の祖という名を刻むことになったのである。その名を渋川伝次郎、人呼んで渋伝。敬称も渋伝先生といわれるくらい、人々に親しまれ敬愛された。
優等生“骨皮(ほねかわ)”
伝次郎は1898(明治31)年父渋川藤之助・母ゆみの二男として、黒石町前町7番地に生まれた。渋川家は黒石の旧家岸谷の筆頭分家だったといわれ、祖父伝蔵が商業を営んで大をなし屋号を岸藤といった。伝次郎が学校へ上がるころは魚問屋・藁工品(わらこうひん)移出業・旅館を経営し、前町の店(今のマルチ商会の辺り)は間口20間(36メートル)もあったという。

祖父伝蔵は進歩的で器量(才能・徳性)の大きい人物で、明治時代の自由民権派と交わり、その縁でこの地方初の大りんご園「興農会社」の株主になり、その生産するりんごの販売を一手に引き受けていた。父藤之助も気迫のある人物で、遠く弘前の旧藩練兵場あとに開いた大りんご園に投資して、後に9.6ヘクタールを自ら経営することになった。当時、水田をたくさんもっている地主や大きい商人が、りんごに投資するのがはやった時代で、土地の安い中津軽郡清水村(現弘前市)や東津軽郡新城村(現青森市)などに黒石商人がたくさんりんご園を開いたものである。
渋川家では長男伝之助に家業をつがせ、二男の伝次郎にりんご園をやらせることにした。だから伝次郎は五所川原町に開設された県立農学校に進学した。1913(大正2)年のことである。この年、新城村にあった県農事試験場を黒石町に誘致することになり、黒石にあった南郡立農学校舎をそれに当てるため、農学校は五所川原町にあった北郡立農学校に合併し、県立農学校となったものである。後の五所川原農学校である。
思いがけない学校の移転は、多くの生徒の運命を変えることになった。黒石ならば通えるが五所川原の寮に入るのでは経済的に困るという生徒がたくさんいた。それに、この1913年という年は米の大凶作の年で、五所川原へ行った生徒でもあとで退学する者が多く出た。
伝次郎は父にいわれたという。
「お前を学校にやるのに1町歩の水田のあがりをつぎこまねばならないのだから、しっかり勉強するんだぞ。」
1町歩すなわち1ヘクタールのあがりというのは、10アール6俵の米がとれるとして、その小作米(現物でとる貸付料)は3俵、1ヘクタールでは30俵が学費・寄宿舎食費・小づかいなどにかかるという意味である。恵まれた少数のものだけが進学できたのである。
伝次郎に父の心配は無用であった。生れつき優秀な頭脳に勤勉さを備えていた。農学校の3年間を1番でとおし、卒業式では臨席の県内務部長から銀時計を授与された。そのことについて伝次郎は「なあに、予習復習をきちんとやっただけのことですよ。」と簡単なことのようにいう。しかし、そのやり方は決して尋常(普通)でない。放課後は級友と楽しく遊び、勉強は早朝に起きてやったのである。
春や秋は学校の実習用温室が快適だった。夏はどんなに暑い日でも早朝の校庭の土や草はひんやりとしていた。冬は炊事場の大きな囲炉裏の傍(そば)にしゃがんだ。火種を灰の中に埋めてあるので暖かであった。
級友は成績のよい勤勉な伝次郎を敬遠するようなことはしなかった。よき遊び仲間であったからだが、彼が小柄で痩(や)せた少年だったからでもある。みんなは「渋川」とは呼ばず「骨皮」と呼んだ。卒業時、彼は身長158センチ、体重49キロしかなかったのである。尋常小学校6年、高等小学校3年、農学校3年の時代だから18歳の年のことである。それが20歳のときには167センチ・60キロと大きくなっていた。渋川語録が一つ生まれた。「男は二十歳の朝飯前まで育(おが)るものだ。」
悲しい退場
農学校を卒業した伝次郎は、黒石の実家で休む暇もなく、清水村のりんご園に移った。すでに剪定の作業は始まっていて、古くからの使用人仁作爺(にさくじ)さまの手ほどきで仕事をしなければならなかったのである。卒業記念に五所川原で買った鳥打帽をかぶり、母が作ってくれたふっちゃぎ(裾の横に切りこみをつけた短い着物)に、これも手縫(てぬ)いの股引(ももひき)をはき、その上に脚胖(きゃはん)をつけて藁(わら)くず(雪道用の藁で作ったスリッパ状のはきもの)をはき、その上に木靴(といっても木の箱)をはき、それを縄で何重にもしばったので、ぽかぽか足はほてった。汗をかいて帽子をとることが多く、いつの間にか帽子をかぶらなくなった。吹雪になってもかぶらないので、人夫たちは「渋川の空(から)頭」と呼んだりした。
りんご園には渋川西園という名がついていて、その作業日誌と経営記録をつけるのも伝次郎の役目であった。渋川家では山形村福民の興農会社解散で現物配当を受けたりんご園3ヘクタール余もつくっていて、これが渋川東園である。西園は確かに黒石の西だが福民は黒石の南である。黒石を中心に考えたのではなく、要するに東西にあるということだったのだろう。

西園の所在地はくわしくは清水村宇和野(うわの)で1000ヘクタール余もある台地の西のはずれの方にあった。北西には岩木山がその中腹をせり出したように迫り、南東には久渡寺山が望まれたが、一番近い下湯口の集落でも1キロも離れていて、人の往来がないのが辛かった。特に青春多感の時期、黒石にはたくさん友達がいるというのに、ここでは一人の話し相手もないのである。ひとりでに手紙を書くことが多くなり、その返事を待ち焦がれる日が続いた。夜はランプのもとで本を読むしかなかった。
春4月になって通常の作業が始まると、りんご園はにぎやかになったが、若い支配人にはこれが又苦労であった。遠く黒石からの出作(でづくり)(他村にある田畑に出向いて耕作すること)であったから、小沢)、悪戸、下湯口といった周辺の集落には血縁も地縁もない。そういうところで季節によっては1日6、70人の人夫を集めなければならなかった。9.6ヘクタールといえば今でも指折り数えることができるほどの農家しか持っていない大きい面積である。それがまた南北に細長く、その距離は200メートルもあった。園地に凹凸があり、排水のため深い溝を掘ってあったから、人夫の中にはそこに隠れて骨休みしたり、中には袋かけをさぼって、渡された袋を土に埋めるようなことをするのもいた。若い支配人に、そういう人夫たちを手足のように動かす術があるわけはない。結局持ち前の大声で叱(しか)ったり励ましたりするほかなく、その声が下湯口まで聞こえてきたという伝説がある。実際風向きによっては聞こえたかも知れない大音声の持主でもあった。
伝次郎はここで20歳になって兵役の義務を果たし、ここで新婚生活を送り、そして2人の子を得た。大きなりんご園経営が病虫害のまんえんで苦しくなっていたときであったが、一生懸命働いた成果はあがっていて、将来については少しも不安をもっていなかった。そこへ父藤之助が突然やって来て、「西園を閉める。黒石へ帰って東園の方をやってくれ。」と言われたときは、口もきけないほど驚いた。渋川家の多角経営がうまくいかなくなって、西園へこれ以上投資できなくなったというのである。日誌と記録は欠かさず記入していたが、肥料・農薬は黒石から届けられ、収穫したりんごは父が黒石へ運んでいった。 支配人といってもそれだけの存在でしかなかったのだ。伝次郎は悄然と(しょうぜん)して雪の宇和野を後にした。1923(大正12)年25歳の3月であった。6年前一人で赴任した彼に、今は前途を案じる妻と何事も知らない2人の幼児が従っていた。
大正の新しい思想の中で
伝次郎が宇和野にいた間に、日本の社会は大きく変り、黒石もまたその流れの中にあった。すなわち第一次世界大戦で日本は高度の経済成長をとげたが、戦争が終わると不況がやってきて、多くの企業が倒産した。渋川家もその不況を乗りこえることができなかったのである。
経済成長は、反面、国民の政治的、思想的自由への目ざめをうながした。後に大正デモクラシーと呼ばれる自由主義的、文化主義的風潮があふれ、伝次郎の友人たちも熱っぽく民本主義や社会主義を語り、小説や詩や短歌をつくっていた。生活の基盤がまだ安定せず、しかも2人の子の親になっていて、青春気分でいられる伝次郎ではなかったが、敏感な好奇心から北岡義端(ぎたん)や柴田久次郎、境義雄といった文学青年、左傾青年の仲間に入っていった。宇和野で文芸雑誌「希望」を購読し、翻訳ものではトルストイやドストエフスキーなどを読み、日本のものでは徳富蘆花、倉田百三、蓮沼門三、西田天香といった教祖的な人道主義者の本に親しんでいた伝次郎には、すでに彼等と共通の基盤ができていたのである。
それは、いってみれば国家という重苦しいもののほかに、社会というものがあり、そこでは老若男女差別なく、その人間としての権利を尊重されるが、そのためにも人は個人として教養を身につけて真の豊かさを求めなければならない、といったものだったのだろう。
伝次郎がそのことの大切さをただ心で思っているだけでなく、生活の上で実践したことがある。1927(昭和2)年春、彼は妻子を引き連れ家を解体して運んで、新城の淡谷悠蔵農園に移り住み共同経営を始めた。青森県の文芸復興期のリーダーとされていた淡谷のトルストイ信奉に共鳴して、利己を排し、協力し合う人間の真の生活を追求しようとしたのである。この共同生活は半年で解消することになるが、彼の純粋で一途(いちず)な生き方を伝えて余すところがない。
生家の没落に加えて、青年期をこのように高価な―プラスの意味でもマイナスの意味でも―道草を食った伝次郎に、平坦な生涯があるわけはない。49歳で最後の俸給生活を終えるまで、実に10回職業を変えている。恐らく「岸藤のオンチャ(二男)なんぼ腰落ち着かねば」と笑われたり、嘆かれたりしたことがあったろうが、事実は、まことに充実した、着実に自分を大成させる道を歩いていたのであった。
10回という転職に共通していることが二つある。
一つは、すべてりんごに関係する仕事で、研究・指導・移出業者の立場での販売・生産者の立場での販売・加工開発販売とあらゆる分野を担当して、りんごのオールマイティー(なんでもできる)人間になったことである。
二つは、短いもので1年足らず、長いものでも4年にすぎない在職期間であったが、必ず与えられた仕事に熱中して人の認めるところとなったので、転職の際は必ず就職を世話してくれる人が現われたということである。俸給から離れたときは住居を提供し、生活を見てくれるファンまで現われた。それは私心がなく、すべてをりんごの発展に捧げる姿が、人に感動を与えるからである。
県りんご協会を育てる

県りんご協会は、会員が納める会費を主たる財源とする、他に例を見ない自主独立の生産者団体である。1946(昭和21)年創立であるが、これこそ渋川伝次郎がそのもてる思想、知識、経験のすべてを投じてつくったものである。もちろん多くの人たちの協力があったが、準備から結成までを指揮したのは彼であるし、結成後は実質的最高指導者として育成に当り、それを土台にして、県下りんご界に大号令を下したのであった。
協会の性格とその果たすべき役割は、三角形の三つの頂点を槍(やり)のように使うことだという。一本の槍は、絶えず法律や政策を勉強して、国や県に対して具体的な建策をすることである。もう一本の槍は、りんごづくりが勉強をし、他産業の従事者に辱し( はずか)められることのないよう、ものの考え方、見方をしっかり持つということである。最後の槍は共同で、規模の小さいりんご農家は、今の世の中の仕組みの中では生きていけないことを自覚して、協力し合うということである。
こういう目標で事業をやっていく限り、協会は存在しているだけで、生産者が生産者を守る、実力のある抵抗団体になる。行政の下請けの外郭団体でもなければ、行政に圧力をかけて何かを得ようという団体でもない。りんごづくりによるりんごづくりのためのりんごづくりの団体、これが抵抗団体としての協会のあり方であることを伝次郎は身をもって示した。
ある時は県知事の無策を面と向かってなじり、ある時は奉仕の精神を忘れた公務員にカミナリを落し、協会の財政確立のため「人を見たらカネとれ。」と公言して会費制度を確立した。「百姓をバカにするものがあれば必ず槍を突っこんだ」という個人の信条を、協会の精神に育てあげた。
「渋伝のカミナリは上へ落ちる」といわれた。つまり、権力をもつ者に向けられることが多かったが、それが私憤(しふん)でないところに「渋伝先生」らしさがあった。テーブルを叩(たた)いて、「お前みたいなのは辞めてしまえ!」と怒鳴って、一夜おいて後悔して、周りに手回しし、本人にも「辞めないでくれ」と手紙を書くようなこともしばしばであった。
後始末に自ら走り回らねばならないのに、またやってしまうというのは、無私の公憤(こうふん)だからで、やられた方も私怨(しえん)として残ることはなかった。
彼の活躍は単に大号令者であることに留(とど)まるものではなかった。剪定技術を理論的に解明して幾冊もの本を書き、歴史を大切にして史料収集から『青森県りんご発達史』全11巻刊行まで指導し、また社会教育の名講師として村々を回った。必ず要旨メモを準備したが、乗るタイプで、聴衆の反応によって大脱線するので大変な評判であった。
官側も民間も、これだけの人を放っておくわけはない。東奥賞(1955年)、河北文化賞(1956年)、藍綬褒章(1958年)、県褒賞(1959年)、園芸学会功労賞(1973年)、勲五等瑞宝章(1977年)が与えられ、そして1988(昭和63)年、黒石市名誉市民に推戴(すいたい)された。
「なに、時の運ですよ。回り番コみたいのもありますからね。」
と本人は屈託ないが、これだけ受賞が重なったりんご人は他にない。
(執筆者 斎藤康司)