
盛秀太郎の生家は村内でも有数の旧家であり、農業のかたわら代々、木地業(きじぎょう)(木彫材料の木を荒挽(あらび)きし、盆や椀など塗り物でない木地のままの日用器物を作ること)を営んでいた。温湯村(現黒石市)は、古くから湯治場として知られ、農閑期を利用して湯治する人が多かった。
共同浴場を取り囲むように立ち並んでいる客舎は、冬場になるとにわかに活気を呈(てい)するのだった。なかには北海道南部や秋田地方からの湯治客も珍しくなかった。
盛家ではこの湯治客のお土産(みやげ)や日用品として、しゃもじ、杓子、煙草盆、ろうそく台、高盃(たかつき)、子ども用としてはズグリ、変わったものとしては、竜頭(投網(とあみ)の頭に用いるもの)、砧(布地を打ちこなす台)に使う木槌(きづち)などを主に製造していた。
秀太郎少年は小学校時代はなかなかの俊才で成績は常にトップクラスを占めていた。小学校を卒業すると、郡立農学校に入学した。郡立農学校跡は、現在の青森県立農業試験場である。4年制の義務教育すらうけることのできなかった児童もいた当時としては、むしろ恵まれた少年期であった。秀太郎が農学校2年生の時、父元吉が急逝した。長男の秀太郎は、家業を継がねばならなかった。その頃、父元吉はりんご園を大規模に経営していたが、1908(明治41)年、津軽地方はモニリヤ病におそわれ、ほとんどのりんご園が皆無作になった。元吉のりんご園も被害をうけ、生計も苦しく、父の病気と重なり、これらの重荷がたちまち秀太郎の肩にのしかかってきた。
しかし、生活苦と戦いながら、持前の不屈の精神を発揮し、多くの家族をかかえながら木地屋としての技能を身につけた。
生来、器用な秀太郎の作った木製品は評判も良かったが、生活は楽ではなかった。
秀太郎が22歳の時である。親戚づきあいをしていた西隣りの黄檗宗(おうばくしゅう)薬師寺住職の義弟の佐々木という宮城県立佐沼中学校の生徒が、薬師寺を訪れた際、その地方のこけしを秀太郎に見せ、こけし作りをすすめた。好奇心の強かった秀太郎は、伝統的な湯治場産業としての土産作りに、あきたらなさを覚えていたので、こけし作りに挑戦した。
この国随一のこけしの始まりである。
1918(大正7)年6月、秀太郎は常盤村榊(さかき)の高木という農家から、スナを妻に迎えた。スナは数え年18歳。当時は結婚年齢が早く、農村地帯では小学校も満足に終えずに、16、7歳で嫁ぐのが普通であった。スナを迎えた半年後の12月、父元吉が亡(な)くなった。
その頃は、第一次世界大戦などで、国内の政治、経済は混乱がひどく、主食の米の相場が高騰し、全国いたるところに米騒動が発生していた。
津軽地方では、この年から数年間りんごの不作が続き、農村地帯はとくに不景気におそわれていた。
農家で嫁をもらうことは労働力をふやすことを意味する。スナも嫁入り後すぐ、作業場でろくろをまわすことになった。なれないうちは指に血豆ができ辛かった。夫婦は木製品を作り、湯治客に売ったが、さばき切れず、生計を支えるためには、杓子、柄杓(ひしゃく)などを背負い、黒石町の雑貨商におろして歩いた。時には約20キロ離れた弘前の和徳町まで足をのばした。1時間で約4キロぐらい歩くので、弘前に着くのはいつも昼頃になった。

背中の製品は夫婦の思う値段で売れることは少なかった。無理に頭を下げて売ろうとすると、足元をみすかされ、散々値切られることがくり返され、疲れた足どりで帰宅するのは夜になることが多かった。
手まわしのろくろから、今日のようなモーター式に改良されたのは昭和に入ってからである。近くの山谷という木地師はそれまで、水車を利用してろくろをまわしていた。
ろくろが手動から電動にかわったものの、金属製の日用品が普及してきたので、木製品の売れ行きが鈍り、夫婦の生活は依然として苦しかった。
秀太郎の字は独得の個性があり、幾ら書いても疲れない字体なので、近所の人々からよく頼まれて出向いた。祝儀の目録、葬儀の香典控え、商品の売り出しポスター、戦時下の兵士の入営の際の幟(のぼ)り、丑湯祭りに行われる薬師寺境内の素人相撲のにわか作りの桟敷席にはられる寄進者の名簿、あるいは役所や警察署等に提出する諸届出書、また、近くの劇場の看板は、ほとんど秀太郎の手になるものが多かった。旧山形地区では女子どもでも秀太郎の書いたものを見ると、「あっ、これは盛秀の字だ。」とわかるほどなじんだものだった。しかし、秀太郎は祝いごとや仏事に呼ばれ書き役を頼まれても、ただの一度も酒を飲んだことはなかった。生涯酒は口にしなかった。
1945(昭和20)年4月、毛内地区(旧山形村)の松根搾油(しょうこんさくゆ)工場から出火し、折からの強風にあおられた火の粉が、対岸の下山形村に降りかかり、消防施設の貧弱なこともあり、またたく間に40数戸が類焼するという、まれな大火が発生した。この時、秀太郎は罹災者の窮状を思い、幾日も費やして、しゃもじ、杓子を作り、一軒毎にしゃもじ1枚、杓子3本・ひしゃく1本ずつ配って歩いた。平素、地域民にお世話になっているという職人気質(かたぎ)の秀太郎としては、当然のことをしたまでのことであり、人に語ることはしなかった。
1955(昭和30)年の4月、弘前の知人の家で、たまたま盛秀太郎のこけしを目にとめた板画家棟方志功は、その魅力に引かれるままに、秀太郎に一通の手紙を送った。文面の結びに「……現存の作品はこの国一番とわたくしが折紙をつける次第であります。」とあった。棟方志功らしい率直な感慨がのべられていた。
地元の新聞は「この国随一のこけし作り」と報道した。
翌年の夏、棟方志功は案内されて秀太郎の仕事場に立ち寄った。10数平方メートルのむさくるしい仕事場であった。
志功は前年の6月、イタリアで行われたベネチア・ビエンナーレ版画展で、「柳緑花紅」(やなぎはみどりはなくれない)外10点が国際版画大賞を受け、その国際的名声はゆるぎないものになっていた。
秀太郎は愛用のゴールデンバットを口にくわえ、1本は左の耳に挟んでの常に変わらないポーズであった。郷土出身で参議院議長をつとめた佐藤尚武が訪れたときでもそうだったが、どんな著名人が見えても一般の人が見えても、その接する態度は一貫していた。相手にあわせてよそゆきの服装をすることはなかった。
か細い三日月型の眉、切れの長い瞳に被(かぶ)さるような八の字型の睫毛(まつげ)、小さな鼻に可憐な口もと。くびれた胴部の下には、素朴で愛らしい表情とは反対の、凄い形相の達磨の絵柄。これらのものが渾然(こんぜん)と調和した扇型のこけしは、秀太郎がこれまでに、地蔵型や棒型を作ったりして、苦心の結果、ようやく到達したものであった。
棟方志功は強度の近視のため、舐めるように秀太郎の、大きめに作ったこけしを眺めていたが、「やはりこの国一番のこけしだ。」と賛嘆の声を惜しまなかった。帰りしなに無地のこけしを貰い、あとで絵柄を書いて送ることを約束し、秀太郎と別れた。
当時、わが国は神武景気で輸出産業が大いにふるい、国民の生活も安定しつつあり、こけしブームも静かに起こっていた。
国際的な名声を得た棟方志功の言葉が記事になるや、秀太郎へのこけし依頼がとみに増えはじめた。しかし、納得のいかないこけしは作らない一徹な性格と、年齢も60を超えていたため、相次ぐ注文にはとても応じきれない日々が続いた。
このままでは名匠といわれる秀太郎の創造した温湯系のこけしが一代限りで消滅することを危んだ黒石市観光課の職員が、後継ぎの必要性を盛家に訴えた。秀太郎の長男は、少年時代の怪我(けが)で家業を継ぐことはできなかったし、孫たちはまだ幼かった。
白羽の矢がたったのは奥瀬鉄則であった。長男真一の嫁の弟であり、奥瀬家の三男に生まれた鉄則は家事を手伝いながら、地元の定時制高校に通っていた。
その年の8月末、鉄則少年は県立黒石高校山形分校1年に編入され、工人としての第一歩を踏んだ。当時はまだ盛家にりんご畑が残っていたので、畑作業をしたり、秀太郎のこけしの原形をかたどる、いわゆる木取りをし、夜間は定時制高校に通う毎日が3年以上続いた。
その頃になるとこけしの引き合いが多く、秀太郎はこけし作りに専念していたが、時折、ろうそく台、ときには市内の宮大工から擬宝珠(ぎぼし)などが持ちこまれることもあり、鉄則も手伝わされることがあった。
字を書くことの好きな秀太郎は、依然として劇場の看板書きは続けており、忙しくなると長男に書かせたり、仕事がつかえてくると、鉄則を動員することもあった。

「良いズグリは良くまわる。」というのが鉄則に対する秀太郎の口癖であった。材料をケチらず、適当な肉厚のズグリは、まわしてもバランスがとれ、長い時間まわり続け、子ども達に喜ばれるというのが秀太郎の持論であった。
ズグリには俗に、上縁部の肉の厚さが変わらない皿ズグリと、上縁部がまるく膨らみ部厚(ぶあつ)にできているカブズグリ(カブは蕪(かぶ)のことで形が似ているのでカブズグリと呼んだ)と二種類あり、秀太郎の皿ズグリは内部の描彩(びょうさい)が華麗で、よくまわるので子ども達の人気があった。温湯地方では、毛利という木地師のカブズグリと秀太郎の皿ズグリが最もよく売れていた。
秀太郎は継承者である鉄則に、手をとり、足をとる教え方はしなかった。「芸は盗め」というかたくなな職人気質がそれを許さなかった。鉄則のこけし作りの技法がだんだん上達しても、決して口にだしてほめることはなかった。また、大声で叱(しか)ることもなかった。無口な名工と、その真髄(しんずい)をきわめようとする弟子とのたんたんとしたこけし作りは、およそ13年続いた。
鉄則にとって、師秀太郎のことで特別に思い出深いことが二つある。
こけし作りを始めて間もない頃、頼まれて「東京こけし友の会」に作品を送った。この作品は素人くさいが、初々しい感覚にとみ、好評を博した。そのことを師に話したら、無言で湯呑み茶碗を投げつけたという。しかも、弟子に絶対に当らない方角に向かって。未熟な腕で職人の面汚(つらよご)しだ――完全主義者らしい師の愛情の表現だったと鉄則は受けとめた。
1986(昭和61)年5月、宮城県白石市で恒例(こうれい)の「全日本こけしコンクール」が開かれた。この席で鉄則の作品が、「内閣総理大臣賞」受賞の栄に浴した。こけし工人の最高の名誉であった。
それより17年前、既に鉄則は黒石市柵ノ木に独立、こけし作りを始めていたが、この朗報を師秀太郎に知らせるため、盛家に足を運んだ。
師秀太郎は高齢で体が衰弱し床に臥していた。枕元で鉄則が報告すると「その賞状をこの部屋に飾れば、部屋が明るくなるな。」と素直に喜んでくれた。“これらのことが一番印象に残る”と鉄則は述懐する。このあと約2ヵ月後、秀太郎はこの世を去る。
鉄則が入門した2ヵ月後、佐藤善二が秀太郎の門を叩(たた)いた。善二は西郡木造在の出身であり、地元の農協の役員をしていたが、内部事情により辞して、上京し、一時、小田原市で観光こけしなどを作っていたが、志を得ず当時父のいる温湯に身を寄せていた。善二の父と秀太郎は昵懇(じっこん)の間柄であった。

善二の県立木造中学校の恩師は横山武夫である。当時、県副知事をしていた横山武夫は善二が失業していることを聞き、目先を変えて、温湯にいるならこけしでも作ったらどうか、とさとした。善二が小田原で観光こけしを手がけた経験も知っていた。父同士が親友であり、恩師のすすめもあって秀太郎に入門した善二だが、年長の故もあって、善二の弟子としての生活は、鉄則と対照的であった。 鉄則は秀太郎の創造した伝統こけしの継承者として自他共に許していたが、善二は気楽に半ば、秀太郎とは没交渉的な形で作業を続けていた。作風も秀太郎と異なっていた。秀太郎も善二の個性を、強いて同化させることもなく、気楽に振るまわせていた。
1960年代に入るとこけしブームはますます高くなり、それにつれ秀太郎の工人としての声価は押しも押されもせぬものになっていた。
1960(昭和35)年 青森県褒賞
1973(昭和48)年 黒石市褒賞
1974(昭和49)年 青森県文化賞
1976(昭和51)年 青森県知事表彰(卓越技能者)
1977(昭和52)年 労働大臣表彰(卓越技能者)
1978(昭和53)年 勲六等瑞宝賞
1982(昭和57)年 黒石市無形文化財指定
受賞の主なものである。このように数多くの栄誉に浴したものの、晴れがましい授与式に、秀太郎自身は一度も出席したことがなかった。ほとんどが長男真一、妻ハツヱが代理出席をした。主催者は、長男の嫁と紹介するのが体裁が悪いのか、「盛秀太郎ご令嬢」と紹介するのがお決まりであった。独自のこけし工人として、その工芸技術が評価され、黒石市無形文化財の指定書は、秀太郎の家の近くの山形公民館で渡されたが、その時でも彼は出席せず、こけし作りを始めていた孫の美津雄が代って出席した。
こけしの色つけは、日中は来客やら騒音で気が散るので、どうしても深夜に及ぶことが多かった。秀太郎にとって、体力の衰えた晩年のこけし作りはかなり体にこたえたと思われる。
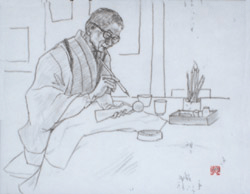
秀太郎こけしは、顔は魅惑的な表情をしているのに対し、胴部の達磨はすさまじい形相である。(本人の思いとは別に)その組み合わせが識者の話題になることがある。
浪岡町本郷凧の影響であるという見方もある。しかし秀太郎の衣鉢(いはつ)をつぐと目されている奥瀬鉄則は、青少年期の家庭的な逆境を乗りきったこと、壮年期に8人の子供のうち、4人と死別したこと、長男の事故による片腕切断、末子の突然の失明など、相次ぐ過去の禍いを振りかえり、七転八起の体験を達磨の図柄に託していると信じている。 頑健な体力を誇っていた秀太郎も90歳の坂を越えるとさすがに弱ってきた。床に臥す時が次第に多くなった。
1986(昭和61)年7月27日、秀太郎は老衰により、身内の者や弟子鉄則たちの見守る中、92歳で一生を終えた。
周囲の人が息を引きとったことに気がつかないほど、安らかな大往生であった。
戒名は「木形院快翁寿慶居士」。木地挽きとして一生をまっとうした秀太郎にふさわしいおくり名であった。
これまで盛家を守り、夫秀太郎を陰に陽に支えてきた妻スナは、夫と前後して病の床にあったが、夫の死後8日後の8月4日、夫秀太郎の後を追うようにこの世を去った。
今、落合にある津軽こけし館は、全国からの見学者で賑わっている。こけしにちなんで始められた「こけしの里マラソン」も全国的に有名になった。こけし館には現在、秀太郎こけしを中心に全国各地のこけしが2700本あるが、ことの起りは山形地区の人々が東北各地のこけしを収集したことによる。収集が成功したのは、秀太郎の盛名を慕って寄贈した工人が全国にいたからであった。
盛家では、今でも毎朝、秀太郎の遺影の前に、生前彼がこよなく愛煙したゴールデンバット1本を、欠かさず供えるのが習慣になっている。
(執筆者 佐藤義弘)