
「黒石卓球界の最大の恩人は誰であるかと問われれば、ちゅうちょなく、それは松井禮七氏であると答える。」棟方守貞(むなかたもりさだ)先生の言葉である。
棟方先生は長く教職にあり、黒石市教育委員長も務めた人だが、なによりも卓球界の草分けとして、82歳の今日なお、かくしゃくとして後輩の指導にあたっている。その棟方先生が「大恩人」と呼ぶのだから、松井禮七の果たした先覚者としての役割は大きい。
松井禮七は1887(明治20)年5月15日、黒石市赤坂に生まれた。宇野兵三郎、みちの五男である。兄に宇野律五郎、宇野海作がいる。1913(大正2)年黒石市横町の薬種商、松井七兵衛の養子となり、後に松井七兵衛を襲名する。旧制八戸中学校から東京歯科医学専門学校に学び、卒業後は同校の教授となるが、学生時代は卓球選手として活躍し、東歯チームの第一次黄金時代を築き上げる。
1914(大正3)年、東歯コートで第7回東京連合ピンポン大会が開かれた。その時の松井禮七の奮戦記を、「東京歯科医専卓球部創立20年史」(昭和9年4月発行)から写し取ってみる。
東歯選手は折り重なって討死してゆく。決勝戦近くなってみると、わが輩ただ一騎。剣は折れ鎧の袖が千切れるとも、最後の一人まで首をかきあげれば、己が楯に乗って帰らんと、悲壮なる決意は遂に私をして栄冠を得せしめた。『壁』というニックネームがつけられたのはこのときである。
講談調の語り口は松井禮七その人の文章だが、「試合は技のものに非らず、心のものなり」と強調するのもまた禮七その人であった。
そして禮七は、日本卓球界草創期の指導的役割を果たすことになるが、1919(大正8)年には「第1回連合卓球大会」が東京日々新聞社(現在の毎日新聞社)の後援で開かれた。大新聞社が卓球大会を後援するのは初めてのことで、大きな反響を呼んだが、これが実現したのは松井禮七の奔走による。この大会では、時の東京市長田尻稲次郎博士がサーブを松井がレシーブをして始球式を行なった。卓球大会の始球式はこれまた初めてのことである。
1921(大正10)年、当時、大日本卓球協会副会長で、東京歯科医専の教授であった松井禮七が来青した。そのころの卓球といえば、板のラケットでショート一点張りであったが、禮七はロングやカットなどという最新技術を持ち込み、科学的な指導を行ったのである。本県卓球界にとっては、まさに一大転機を迎えたといってよい。
その同じ年、青森市に散在していた各チームが集まって、青森ピンポン協会(現在の青森県卓球連盟)が誕生した。協会設立は本県として最初のものであった。もちろん松井禮七の助言によるものである。
また県内の有力選手を東京歯科医専に引っぱって、トップクラスの選手に養成し、これらの人たちが青森県に帰って現役選手となり、あるいは指導者として、本県卓球の土台を作りあげたのである。だから松井は「青森県卓球の父」ともいわれたが、青森県ばかりでなく、広くわが国卓球界の発展のために、大きな力となったことは言うまでもない。
ここで、棟方守貞先生の思い出話から振り返ってみよう。
棟方先生が松井禮七と初めて会ったのは1928(昭和3)年のことである。そのころの卓球は、いわゆるピンポンに毛がはえたようなものであった。カチャカチャと打ち合っていたにすぎない。そんなとき、松井先生が黒石にやって来た。
「ただもう、唖然とするばかりでした。」
なにせ、台から3メートルも離れて、フォアにバックに自由自在に打つのである。1920(大正9)年の夏、県立弘前中学校(現弘前高校)1年生のときからラケットを握ったという棟方先生だが、この松井卓球のスケールの大きさには、ただただ、たまげるばかりであった。
当時、棟方先生は青森師範学校を卒業して上北郡の学校に勤務したあと、若き教師として、ふるさとの黒石市六郷小学校に赴任してきたばかりであった。
すでに黒石では1925(大正14)年に黒石卓球クラブ(黒石卓球協会の前身)が結成されており、卓球のことなら、いささか知っているつもりでいたのだが、松井禮七の技(わざ)を目前にしては、驚くほかなかった。
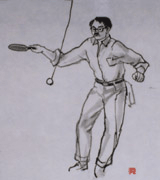
松井禮七はその後、東京歯科医専の教授をやめて、青森市新町(現在の松木屋デパート裏)に歯科医院を開業するのだが、黒石市青山に住む、三女の水木和子は、そのころの父、禮七のことを、思い出し思い出ししながら、かみしめるように語ってくれた。
「たまにですけど、病院の父の居間をのぞくことがありました。すると天井からゴムひもでピンポン玉を吊るしているのです。家の中にいても卓球の練習をしないと気持ちが落ち着かないのでしょう。」
「ときにはこんなこともありました。相撲の回しを締めて、相撲の型というのか、そんなことをやっていたことを見た覚えがあります。」
和子さんがまだ女学校にあがるかどうか、そんな少女時代のことである。
居間の壁には、風呂屋にあるような大きな鏡が置かれており、その鏡に、回しをしめた裸身を写しながら、気合いをこめて心身を鍛えていたのかもしれない。
松井禮七は、相撲にもまた並々ならぬ興味を持っていた。1941(昭和16)年の「月刊東奥」7月号に、「津軽の大力士、岩木川萬之助(いわきがわまんのす)」と題する読み物を掲載している。筆名は松井七兵衛とある。その「はしがき」を断片的ながら紹介しておこう。
「次代を担う国民の体位向上を要求すること今日ほど緊迫したときはない。昔から形こそ異なっているが、時代と国情に応じて絶えず国民の錬成を続け、今日の歴史を産み出したことをとくと考えてもらいたい。
私は昭和4年、養父の死によって、国に帰ってきたが、亡父の持った政党関係は一切返上して、もっぱらスポーツに余力を傾ける決心で、天職以外には運動奉公を念じてきた。
昭和16年の7月といえば、太平洋戦争に突入する直前で、日本は戦時体制一色に塗りつぶされた時代である。その暗い時代に、スポーツの振興を声を大にして提唱したのである。
卓球に相撲に、いささか尽くしてきた関係上、卓球の歴史を整理し、次いで相撲の昔を調べ始めた。たまたま兄が発起人となり、私の生まれた六郷村赤坂(現黒石市)の八幡宮に、村が生み出した力士、一つ森岩吉氏の碑を建てることになった。記事を拾い集めている間に、岩吉の叔父にあたる岩木川萬之助の錦絵と戒名とが兄の目にふれ、つぎつぎと材料を集めて、この一篇をまとめることになったのである。」
岩木川萬之助のことは、ここでは多くを書かない。1846(弘化3)年、南津軽郡山形村毛内(現在黒石市)に生まれ、1879(明治12)年6月20日、34歳で巡業途上、札幌の客舎で急死す、とだけ伝えておこう。この岩木川の追善碑は、温湯の遠光寺(おんこうじ)にある。また一つ森岩吉は1866(慶応2)年4月5日生まれ、1934(昭和9)年8月4日死す。黒石市赤坂の八幡宮境内にその碑がある。
この八幡宮の境内にはかつて土俵がつくられており、村の若者たちの力試しの場であった。赤坂の宇野家の庭にも土俵があったというから、禮七は子供のころから相撲が好きであったのだろう。「月刊東奥」のなかで「卓球の歴史を整理し」と書いているが、残念ながら、卓球そのものについての論文はさがし出すことはできなかった。
青森市の歯科医院が敗戦直前、1945(昭和20)年7月28日の青森大空襲にあい、家財とともに多くの資料を焼失したからに違いない。あす疎開する手はずを整えて荷造りをまとめていた矢先の大空襲であった。
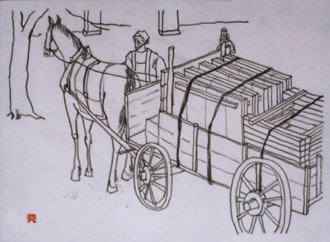
その戦争が終わるずっと前、斉藤一郎さん(故人)は松井七兵衛サマに奉公していた。通称、孫弥損徳(まごやそんとく)の名で親しまれる斉藤一郎さんは、かつては黒石市会議員であり、いまは東奥日報黒石販売店店主として悠々たる生活を送っていたが、小学校を卒業するとすぐ、丁稚奉公に出るという苦労人であった。
その「斉藤一郎回想録」(昭和60年12月、烏城出版社発行)から、松井禮七のくだりをお借りしよう。
私が七兵衛サマにいたころ、もう一人、若旦那がいた。赤坂の宇野海作家から養子に入った人で、禮七という名前であった。彼は医学博士で、万能スポーツマンといわれていた。かつてヨーロッパに留学したとき卓球に興味を魅かれ、それを母校に持ち込んで、日本卓球界の草分けとなった人である。禮七は若いときから、相撲、柔道、弓道、卓球などに打ち込んだが、旧制八戸中学時代は100メートルの選手でもあり、その記録は長い間、破られなかったといわれる。
そのうえ生まれつきの怪力の持ち主でもあった。私のいたころは、夫人と一緒に東京に在住し、大学の教授をしていたが、毎年、夏休みには帰省して、力試しに興じていた。その怪力ぶりは驚異的なもので、左右の足に米俵を一俵ずつくくりつけ、背中に一俵背負って歩ける人であった。
「まさか、両足に米俵をですか。」
斉藤さんの黒石市一番町の事務所を訪ねて念を押した。
「一歩、二歩と歩くんですよ。たまげてしまいましたね。」というのだ。
聞くところによると、学生時代は大相撲部屋によく出入りし、十両力士といい勝負だったというから、怪力は本物であったろう。
七兵衛サマには卓球台もあって、斉藤さんはよくお相手をさせられた。おかげで町民卓球大会で入賞したこともあったそうだが、その禮七が東京にいる間は、主人(先代七兵衛)の読み終えた東奥日報を郵送するのが斉藤さんの役目であった。
「いま考えてみると、今日、東奥日報の販売店を家業にしているのも、なにかの因縁というものでしょう。」斉藤さんは、つくづくとその昔のことを話してくれた。
ここでまた卓球の話に戻ることにしよう。
松井禮七が黒石小学校女子部を訪ねた。1928(昭和3)年の夏である。当時の尋常小学校は男子部と女子部に分かれていた。ときの校長は体育にかけては自他共に認める福田竹太郎である。ともにスポーツ愛好者同士だから、話のうまが合う。
「この学校に卓球台が何台ありますかね。」
まあ、そんな話から始まった。黒石の卓球のことから全国の卓球界のこと、アムステルダム・オリンピックのこと。世界をぐるぐる回りながらの体育談議は延々2時間に及んだ。一方的に話を聞かされて、さすがの福田校長もけむに巻かれたかっこうである。禮七が帰ったあと、福田校長は側にいた山本康一先生に聞いた。
「山本君、松井先生ずいぶんしゃべっていったが、一体何の話でしたっけ。」
「そうですなぁ、卓球台を寄付するとかいっていましたが、あまりに多くて、わがれへんな。」
しかしそれから1ヶ月ばかりして、女子部の校庭にガラガラと荷馬車が入ってきた。荷台には卓球台がごっそり積み込まれていたのである。
「何百人もの子どもたちに2台か3台の卓球台ではだめです。少なくとも、各学年に1台ずつですなぁ。」「はははははぁ。」そんなあんばいであった。
尋常科(じんじょうか)に6台、高等科に2台、実科女学校に3台、計11台。これは女子部の分。男子部にも尋常科に6台、高等科に3台、計9台。そしてさらに卓球協会に2台と合計22台を寄贈し、自宅に備え付けの2台をあわせると、なんと24台を作ったのである。
2台や3台ならまだしも、これほどの数である。福田校長ならずとも、本気にしなかったに違いない。金があるからといってできる芸当でもない。松井禮七のスポーツにかける情熱と心の豊かさをそこに見る。
そのころ松井禮七は、帰省するたびごとに、鈴木寅之助(すずきとらのすけ)、加藤一誠(かとういっせい)、山本康一、棟方守貞といった人たちを自宅に招いている。
「黒石卓球50年史」(昭和46年4月から22回にわたって津軽新報に連載。筆者は棟方守貞氏)から、そのほほ笑ましいエピソードを綴ってみよう。
松井先生からの招集状は、自筆で雄渾(ゆうこん)な書体のすばらしいものであった。夕方になると、七兵衛サマの店員が、この大きな名刺を届けにくる。
「午後5時、夕飯を食べないで、バットを持ってお出でありたい。」
と書かれている。直ちに参上する。七兵衛サマの表2階の3部屋の襖を外して卓球台を据え付ける。畳なので足の滑るのをがまんし、上の欄間にボールの当たるのに気をつけると、結構、練習に差し支えない。ひと汗流してから、鍋焼うどんをご馳走になりスポーツ談議に花を咲かせる。松井先生は卓球ばかりでなく、庭球も相撲も一流だし、スキーもやった。夜の更けるのも忘れて、談じては卓球をやり、卓球をやってはまた語り合ったものである。
松井禮七のこうした交流は、たんに卓球の技術を伝えようというものだけではないだろう。東京で医学を学ぶ間にも、黒石の町やふるさとの若い人たちとの心のきずなを忘れまいとする愛情から出たものと思う。
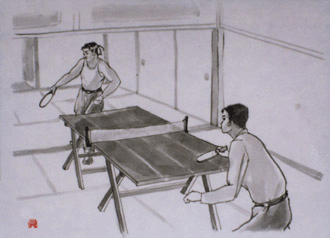
松井家には野口英世博士の金時計がある。財団法人野口英世記念会によると、この金側懐中時計は1915(大正4)年、野口博士が帰国されたとき、血脇守之助(ちわきもりのすけ)先生にご恩を受けたお礼として贈られたもので、松井禮七教授が東京歯科医専を退職するにあたって、記念に感謝を込めて贈られたものといわれる。
野口博士の生涯の恩人とされるのは、郷里福島県猪苗代町(いなわしろまち)の教師、小林栄先生と、英世が上京して身を寄せた高山歯科医学院教授で、後の東京歯科医学専門学校長の血脇守之助であった。その血脇学長が、松井禮七が東京を去るに当たって、野口博士から贈られた懐中時計を禮七に渡したのである。いかに信頼されていたかがわかる。
この金側の懐中時計は現在、東京新宿の野口英世記念会が大切に保存している。松井家が記念会に期限付で貸しているのだが、黒石市にとっても記念すべき宝物といってよい。
好漢惜しむらくは、松井禮七、1946(昭和21)年7月6日、これからというときに59歳で急逝した。

その松井禮七の遺徳を偲んで、「第1回松井杯青森県選抜卓球大会」が開かれたのは1948(昭和23)年である。会場は黒石実科高等女学校の体操場である。会場には松井先生の写真が飾られ、明本常丸先生の読経で三回忌法要が営まれたあと、試合は開始された。県内からは往年の名選手が続々と参加して見事な熱戦であった。戦時中、鳴りをひそめていた卓球熱が、この松井杯をきっかけに、待ってましたとばかり始動したのである。
優勝カップにまつわるエピソードがある。
「松井先生の卓球界に残した功績は大きい。それにふさわしい、一番でっかいものにしよう。」
関係者たちはそう考えた。

鈴木寅之助(すずきとらのすけ)氏と棟方守貞先生の二人は、弘前の街中を朝から晩まで、足を棒にしてカップを探したが見つからない。なにもかも物がなかったころである。だが、松森町の馬具屋(ばぐや)をのぞいたらそこにあった。馬力大会の優勝杯として取り寄せたという高さ1メートルもある大カップである。
「これだ。」
大相撲の優勝賜杯、あの大カップにも匹敵するほどのものだが、値段はなんと当時のカネで1万円であった。そのおカネは松井家のご遺族から寄贈されたのである。この優勝杯争奪戦は選手たちの大いなる目標となったことはいうまでもないが、あまりの大きさに持ち帰るのがひと苦労であった。手に下げて持つことができないから、背負っていったものだという。
名物の大カップはいうまでもなく、別の優勝杯に代ったけれども、松井杯はいまも絶えることなく継続されている。そして松井禮七の残した卓球にかける情熱は多くの人たちに引き継がれ、全国はもちろん世界的な名選手が続々と登場して、黒石卓球の名を高めたのである。
(執筆者 柴田黎二郎)