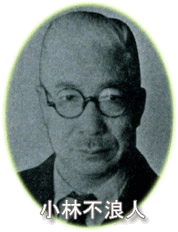
中野神社は、もみじの名所として黒石近郷に名高い。その中野神社の境内の一隅に青森県を「川柳王国」と言わしめるほどにした小林不浪人の句碑が立っている。 碑の表には二つの川柳が刻まれている。
あきらめて歩けば月も歩き出し 不浪人
動中に静を求めて煙草の輪 不浪人
人間は多くの煩悩(悩み・迷い)を持っている。そして、その煩悩を断ち切ろうとまた悩む。口語短歌で知られる鳴海要吉は次のように歌う。
あきらめの旅ではあった磯の先の
白い灯台に日は映(さ)していた
煩悩を断ち切る一つの手段はあきらめである。手段ではない。どうにもならなくなって人はあ きらめる。あきらめようとするが、思いは残る。要吉はその思いを尻屋崎(しりやざき)の孤高(ここう)の白亜(はくあ)の灯台に託した。不浪人は月にその思いを懸(か)けたのである。満月であったか、半月であったか、いずれにしても、お月様は優しい。「よし、あきらめよう。」と決心し、天を仰ぐとお月様が僕を見ている。僕が歩くとお月様も一緒に歩いてくれる。「あきらめて」の句はそんな心境を17字音(じおん)にしたのではないか。どんな煩悩かは知らないが、煩悩を持つ「人」の共感を呼ばずにおかない。
「動中静あり」という言葉が昔からある。騒ぎや多忙の中にあっても冷静でなければならないという教えである。戦国の世の武士が好んだ言葉である。今の時代でも、仕事は戦争のような所がある。無我夢中で仕事をし、息つく暇も無い。また、一つのことに夢中になって行き詰まってしまうことがある。そんな時「まあ、一服しようじゃないか。いい考えが浮かぶかもしれない。動中静ありというではないか。」と煙草を取り出し、ゆっくり火をつけ天井をあおいで、煙の輪を吹き上げる。「動中静あり」の句はそんな時の心情をうたったものであろう。
現在、たいていの新聞、雑誌に「川柳欄(せんりゅうらん)」がある。
その川柳を見ると、17字音の中で、世の中のありさまやできごとの真相を掘りおこして皮肉ったり、滑稽化(こっけいか)化しようとしていることに気付く。17字音でつくられているから俳句のようであるが俳句とは感じがちがう。
川柳家の三浦三郎(さぶろう)は「川柳入門」の中で、川柳を次のように解説している。
川柳は18世紀中頃、柄井川柳(からいせんりゅう)によって短詩型の文芸の一つとして確立した。(川柳の名称はここから始まる)武士・農民・町人の身分や教養に関係なく、自由な発想のもとに社会の矛盾などを詠むことができる川柳は、江戸時代に大衆の文芸として盛んになっていった。
しかし、大衆によって簡単に作れる川柳は、やがて言葉遊びに流れていく。文字や言葉、また事柄の似ている点やその反対のことを、ことさらにふざけて、駄洒落を乱用して笑わせようとする川柳(狂句と言った)が流行し、それが約100年ほど続いた。
再び、川柳の文芸性を復興しようという動きが出てきたのは明治の後半になってからである。その先駆(せんく)(さきがけ)となった人は、阪井久良岐(さかいくらき)であり井上剣花坊(いのうえけんかぼう)である。
久良岐は「五月鯉(ごい)」、剣花坊は「川柳」という川柳雑誌を1905(明治38)年に出して新しい川柳の啓蒙(けいもう)(正しい知識を与えること)をはかった。それ以後、大正・昭和と川柳は一途(いっと)に隆盛へ向かうのである。
小林不浪人は黒石にあって、文字遊びに化した川柳を復興しようとした東北の第一人者(他に肩を並べる人がいないほどの人)であった。
黒石は昔から文芸の盛んな所である。青森県の川柳発祥の地(初めておこった土地)と言われているが、その母胎となったのは1911(明治44)年、鹿の子(かのこ)(雅号(がごう))・来迎寺住職(らいごうじじゅうしょく)を中心にしてできた「浮雲会(うきぐもかい)」であった。浮雲会は、最初は都々逸(どどいつ)(男女相愛(だんじょそうあい)の情を七・七・七・五の四句を重ねて作る歌謡)を主として作るグループであったが、後に川柳を主とするようになっていく。
小林不浪人(こばやしふろうにん)(本名 野呂長三郎(のろちょうざぶろう)は、1892(明治25)年、黒石町甲徳兵衛町23番地に野呂米太郎の二男として生まれた。20歳の時に母の実家の養子となり、小林姓となる。
不浪人が川柳を始めたのは1910(明治43)年18歳のころで最初は蝶三郎(ちょうざぶろう)と号していた。
明治43年ごろといえば中央で阪井久良岐や井上剣花坊が川柳改革ののろしを上げて、5、6年よりもたたない、いわゆる川柳の黎明期(れいめいき)(夜明けの時期)である。当時は、各新聞が競って川柳欄を設け投句を募っていた(久良岐や剣花坊等がその選者になった)。そのせいもあって、地方にも新しい川柳の波が広がっていた。ちなみに、東奥日報が初めて「東奥柳壇(とうおうりゅうだん)」という川柳欄を設け一般から川柳を募集したのは明治44年のことである。
1913(大正2)年、不浪人は「浮雲会」に入る。
1914(大正3)年、不浪人22歳、現在の黒石小学校の前身である黒石高等小学校(今の市民文化会館のあたりにあった)の教師となる。小林長三郎先生である。体は大きくスポーツマンであった。
「大男の割に神経質」と川上三太郎は彼を評しているが、神経質というよりは人間の心の繊細な動きを察知できる鋭い感性の持ち主であると言った方が適切である。そのような感性によって人間社会の矛盾(つじつまの合わないこと)や人間自体の矛盾性を日常生活の小さな出来事や行動から洞察(見抜くこと)できたのである。
不浪人は黒石小学校に7年間勤めたが、その間、同僚や子どもたちにも川柳を教えた。
当時の不浪人の写真が残っているが引き締まった体と、面長(おもなが)で日に焼けた顔からは文学者というよりはスポーツマンの鋭い気性とたくましさが感じられる。
不浪人は東奥日報の川柳欄への投句だけでなく、当時、日本の川柳界をリードしていた井上剣花坊(柳樽寺川柳会(りゅうそんじせんりゅうかい))の「大正川柳」に積極的に投句し、その才能はいち早く認められ「東北に不浪人あり」と注目されるようになった。
1918(大正7)年8月、「大正川柳」の主要メンバーである川上三太郎のすすめもあって野呂冬山(不浪人の実兄)、山田よし丸、佐々木若坊(わかぼう)らを誘って「川柳みちのく吟社」を結成し、ここに青森県初めての川柳誌「みちのく」が誕生したのである。
青森県に最初の川柳の灯をともしたと言われる「みちのく」も最初は西洋紙四つ折りほどの大きさ(四六版)2ページ、謄写(とうしゃ)刷りのまずしいものであった。しかし、みちのく地方の川柳を開拓し、そしていつまでもそれを培っていこうという気概に満ち満ちていた。
1921(大正10)年、不浪人29歳、小学校教員を退職し、東奥日報社に入社する。青森市に移るとすぐに「みちのく吟社」の青森支部をつくる。また、東奥日報夕刊に「東奥川柳壇」を設け盛んに県下へ川柳の宣伝に努める。
「みちのく」には同人の句が多く載せられているが、一般からも募集していて、県内はもちろん県外からも作品が寄せられている。また、川上三太郎をはじめ当代一流の川柳家を選者にして厳しい批評を受け自らを鍛え、また青森県の川柳の質を高めようとした。
「みちのく」が小粒ながら辛(から)いところを見せ、全国の川柳家から注目されたのは第30号(大正10年新年号)のころからである。不浪人は「みちのく」に「ちび筆(ひつ)」という欄をつくり、ここで川柳の在り方について自分の考えを主張した。そのとき、全国から寄せられる川柳家の句が槍玉(やりだま)にあげられ、厳しい批評の対象になった。後日、不浪人は「尽きせぬ思い出」の中で『ちび筆』について次のように書いている。「……私は柳界(川柳の世界)の誰かが言わなければならないことをズバリ言ったに過ぎなかったのである。しかるに相当誤解もされた。そして誰言うとなく『東北の荒夷(あらえびす)(荒々しい武士)』と言う異名(いみょう)(あだな)をつけられた。」
「みちのく」36号(大正10年7月号)の「ちび筆」は、当時、天下一を誇る川柳誌「大正川柳」を槍玉にあげている。
不浪人は「大正川柳」の中に
四ツ辻(つじ)へ来ると飴屋(あめや)の乱れ打ち
という句をみつけた。当時は太鼓をたたいて飴屋が子ども相手の飴を売って歩いた。子どもは飴屋の太鼓の音を待っている。四ツ辻(十字路)だと四方に太鼓の音が鳴り渡るので飴屋にとっては稼ぎ場所である。勢い太鼓を激しく打つ(乱れ打ち)ことになる。こんな世情(せじょう)を詠んだ句である。
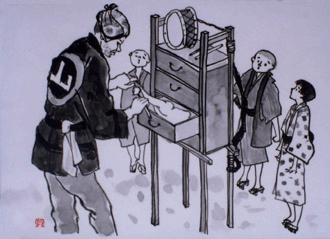
ところが、以前に「みちのく」2月号の中に
お定りの辻で飴屋の乱れ打ち
という句が掲載されているのだ。
『「四ツ辻………」の句は「お定まり………」の句の焼き直しではないか。作者も選者(剣花坊)も「みちのく」を読んでいるはずだ。「みちのく」のようなちっぽけな雑誌は只(ただ)で貰(もら)っているだけで一行も読んでいないというなら別である。読んでいるのなら、「四ツ辻……」は焼き直しだから抹消してしまえと怒鳴る権利はこっちにあるのだ。川上三太郎は「川柳家は作句と同時に他人の句をぜひ読みなさい。」と主張されているではないか。雑誌は大きいから良いというものではない。熱心さと真剣さによって評価されるものである。』
西洋紙四つ折り8ページの「みちのく」で一流の川柳雑誌、しかも、川柳の第一人者である剣花坊に不浪人は警告を発しているのである。
不浪人は他に厳しかったが、より以上に自分にも厳しかった。特に、同じような句や人まねの句を極力排除しようとした。「妥協は詩の上で何はともあれ避けねばならぬ。」だから彼は「みちのく」に出される同人の句を厳しくチェックし、もし以前に誰かが同じような句を作ってあればそれが偶然であろうが容赦なく抹消し、作句者に猛省をうながしている。
川上三太郎は「不浪人は………どっちかと言えば無口でおとなしい方だが、書かせると、これで毒筆(どくひつ)(皮肉のきいた文章)だからね。」と不浪人の鋭さ、厳しさを認める。
この誰にも妥協せず、内にも外にも厳しく川柳を追求していく精神が「みちのく」の伝統となった。そして、そのような研究心やチャレンジ精神が「みちのく」を支え、27年間も継続出版を可能にしたのである。また、その活力が「県下川柳大会」(昭和9年)や「海峡親善(かいきょうしんぜん)川柳大会」(昭和4年から青森、函館の両市で毎年交互に開催)の実施を成功させたのである。
昭和19年といえば、日本は戦争の真最中、しかも敗色が見えてきたころである。産業も生活もすべて戦争に結びつけられ、国民は多くの犠牲を払った。「紙も戦力なり」と言われ、雑誌を発行するための紙の入手が困難になり、27年間続いた「みちのく」も、ついに288号で中断せざるをえなくなった。不浪人、「みちのく」との別れの一句。
いつか芽を吹き出すだろう巨木の根
1945(昭和20)年7月、青森市は空襲を受け、一夜で焼け野原と化した。不浪人も家を焼かれ、黒石町の実家に帰る。
同年8月、4年にわたる戦争は終わった。同年12月、不浪人は待ち構えていたように、新生「みちのく」を再刊した。その巻頭言(かんとうげん)で不浪人は次のように言う。
『戦争がおっぱじまって以来、大方の国民に「笑い」というものが忘れられてしまったのが争うべからざる事実である。新生「みちのく」は、その忘れられていた「笑い」を大方の国民に取戻すことを大きな使命の一つとしなければならない。しかもその「笑い」も、げたげた笑いではなく、また、くすぐりでもなく真実の笑いでなければならないのである。』
再刊された「みちのく」から
平和愛遠慮のいらぬ灯がきれい よし丸
戦争中は、敵の飛行機に見つけられるといけないので、電気の光を外に漏らすことが禁じられていた。人々は暗い夜を過ごさなければならなかったのである。
もう朝だ夜明けだ縄が切れて春 蝶五郎
「朝だ夜明けだ」は新しい時代の到来の喜びであり「縄」は戦争中の多くの束縛の意味である。
戦災の痛手の事は口にせず 不浪人

戦争で多くの人々が家を焼かれ、家族を失った。しかし、人々は悲惨な過去や貧しく苦しい現実よりも新しい出発、明るい未来に目を向けていた。
復刊された「みちのく」は通算306号まで続く。
1948(昭和23)年、県内各地の川柳吟社の代表者38人が集まり、全県をまとめた青森県川柳社を結成し、雑誌「ねぶた」(代表 後藤蝶五郎)が創刊された。と同時に「みちのく」はその長い歴史を閉じることになる。「ねぶた」は「みちのく」を継承しながらも、みんな自由平等の立場で民主的に青森県川柳を盛り上げていこうとしたのであった。創刊当時の同人は、かつて不浪人の下で共に川柳に打ち込んだ後藤蝶五郎、山田よし丸等であった。
「ねぶた」はその後、後藤柳允(ごとうりゅういん)(蝶五郎の長男)が中心となって編集し、柳允没後は中林瞭象(なかばやしりょうぞう)、西谷東山(にしやとうざん)らの手に受け継がれ、現在も継続発行している。
1954(昭和29)年1月19日、不浪人脳溢血(のういっけつ)のため逝去。62歳であった。
青森県川柳人連盟は永くその功績を讃えるために昭和30年「不浪人賞」を制定した。
私の好きな不浪人の句
貧にいて子の素直さを淋(さび)しがり
待って待って待って柳の芽をむしり
母に似た声で喜ぶ女の子
大吹雪後ろを向いたまま歩き
川上三太郎は不浪人の死を悼み、追悼の句を詠んだ。
なつかしや雪の中なる友の顔 三太郎
(執筆者 蒔苗實)